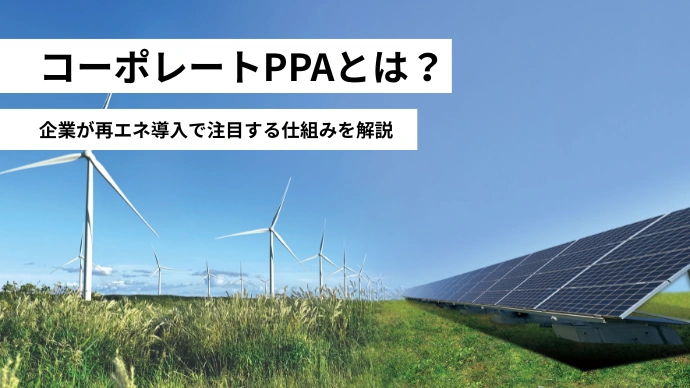脱炭素経営とは? 企業が取り組むメリットと課題、主な取り組みを解説
「脱炭素経営」が注目される中、メリットが分からず、取り組みのイメージが湧かないという経営者や実務担当者もいるかもしれません。本記事では、脱炭素経営のメリットや課題、具体的な取り組みを解説します。
- 脱炭素

脱炭素経営とは
環境省によると、脱炭素経営とは「気候変動対策(≒脱炭素)の視点を織り込んだ企業経営のこと」とされています。
気候変動の影響は、私たちの社会や経済だけでなく、自然環境や生態系にも及びます。地球温暖化をはじめとする気候変動の原因の1つが二酸化炭素(CO2)などの温室効果ガスです。そのため、世界全体でのCO2排出量の削減が求められており、企業活動もその例外ではありません。
従来、こうしたCO2削減の取り組みは、企業のCSR(コーポレート・ソーシャル・レスポンシビリティ、企業の社会的責任)活動の一環として行われることが一般的でした。つまり、事業活動の主目的とは別の活動として位置付けられてきました。
しかし、環境省によると、近年は、環境が持続可能でなければ事業活動が成り立たないという考えから、気候変動対策を自社の経営課題と捉え、全社を挙げて脱炭素経営に取り組む企業が増えているとされています。
脱炭素経営が注目される背景
脱炭素経営が注目されるようになった背景としては、2015年にフランス・パリで開催された国連の気候変動枠組条約第21回締結国会議(COP21)での「パリ協定」が挙げられます。パリ協定では、2020年以降の気候変動問題に関する国際的な枠組みで、「世界の平均気温の上昇を産業革命前と比べて2℃より十分低く保つとともに、1.5℃に抑える努力を追求すること」を196の国と地域が約束しました。
こうした世界の動きがあり、日本では2020年に、2050年までにカーボンニュートラルを目指す、いわゆる「カーボンニュートラル宣言」が発表されました。人為的なCO2の排出量から吸収量を差し引きゼロにした状態を目指すという宣言です。
このカーボンニュートラル宣言を受けて、2021年には、日本のエネルギー政策の根幹をなす「第6次エネルギー基本計画※」が策定され、脱炭素社会の実現を目指す方向性が具体化されました。2023年には、「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(省エネ法)」が改正され、エネルギー使用量が一定規模以上の工場・事業場に対して脱炭素化が求められるようになりました。このように、日本は国を挙げて脱炭素化を目指しており、企業を取り巻く制度やルールの改正が進んでいます。
また、脱炭素などに関する企業の自主的な取り組みを後押しする国際イニシアチブも登場しています。日本企業もこれらの国際イニシアチブに参加しており、大企業だけでなく、中小企業の参加も増えています。主要な国際イニシアチブについては、後述のコラムで詳しく解説します。
- ※2025年2月には「第7次エネルギー基本計画」が策定された。

脱炭素経営に取り組むメリット
企業が実際に脱炭素経営に取り組むことによって、さまざまな面でのメリットが期待できます。具体的にどのようなメリットが考えられるのか、5つの側面から紹介します。
CO2削減を通じた業務改善およびコスト削減
企業のCO2削減の取り組みの一環として、業務の各プロセスでどれだけCO2排出量が発生しているのかを調べることがあります。CO2排出量が多い業務プロセスでは、業務の“ムダ”がありより多くのエネルギーを消費している可能性があります。このようなプロセスを見直して改善することで、結果としてコストの削減が進むことが期待されています。
社会課題に取り組むことによる企業価値の向上
脱炭素経営は、気候変動という地球規模の社会課題の解決に取り組むことに他なりません。脱炭素経営に取り組んでいることを表明することで、こうした企業の姿勢を明確にすることができます。それによって、社会全体の課題を自分ごととして捉え、率先して対策を進める企業として、企業価値の向上につながる可能性があります。
企業価値の向上による人材獲得の可能性
脱炭素経営によって企業価値を向上できれば、それに共感する新たな人材の獲得につながる可能性があります。また、脱炭素経営を行うにあたって企業の存在意義(パーパス)を見直すことは、働く社員やスタッフにとっても自社の方向性を明確にすることになり、モチベーションの向上につながる可能性もあります。
新たな製品やサービスの開発
脱炭素経営に取り組むことは、新たな製品やサービスを開発するきっかけになると期待されています。CO2削減に役立つ新製品・サービスはもちろん、自社の製品やサービスに伴うCO2排出量を削減することで、他社と差別化できる可能性もあります。
補助制度などでの優遇
脱炭素経営にコミットする企業を対象とした補助制度も実施されています。例えば、環境省の「Scope3排出量削減のための企業間連携による省CO2設備投資促進事業」は、「GX率先実行宣言」を行った企業を対象としています。GX(グリーントランスフォーメーション)とは、脱炭素社会の実現を目指して、経済や社会の仕組みを変革する取り組みです。GX率先実行宣言は、サプライチェーン全体のGXを進めるアプローチの1つとされています。
この促進事業では、代表企業とその取引先がCO2排出量の削減に合意することなどが要件とされており、要件を満たす場合には、CO2削減効果の高い設備の導入に対して、中小企業の場合2分の1、大企業の場合には3分の1の補助が行われます。

脱炭素経営を目指す上での課題
脱炭素経営に取り組むことにはさまざまなメリットがある一方で、課題もあります。企業の内部と外部における課題を見ていきます。
専門知識が求められる
脱炭素経営を行うには、CO2排出量の削減などに関する専門知識が求められます。特に、CO2排出量の算定・報告を行う場合には、報告のルールを理解することが大切であり、専門知識が必要とされます。また、脱炭素経営に伴う業務を既存の業務とどのように両立させるかにも課題があります。中小企業などでは、新たに専門の部署やチームを立ち上げることが難しい場合もあるかもしれません。
脱炭素経営をめぐる制度の変化が激しい
脱炭素経営に関連して、国の制度やルールがありますが、こうした制度の見直しのスピードが比較的早いことも課題の1つです。例えば、前述した省エネ法は、2023年に大きな改正が行われましたが、その後も見直しが続けられています。脱炭素経営に取り組む企業は、こうした制度の変化に迅速に対応することが求められるでしょう。
中長期的な脱炭素経営の主な取り組み
脱炭素という社会課題は、性質上、一朝一夕に解決するものではないため、中長期的な視点で取り組むことが重要だと言えます。具体的な取り組み例を紹介します。
省エネに取り組んでCO2排出量を減らす
事業活動には、電気やガスといったさまざまなエネルギーを必要としますが、エネルギーの使用にはCO2排出が伴います。そのため、エネルギーの使用量そのものを減らす省エネに取り組むことは、脱炭素経営の第一歩だと言えます。
生産設備や空調設備などを、よりエネルギー効率が高いものに更新することで、省エネに取り組むことができます。また、建物の遮熱・断熱対策によっても省エネ効果を高めることができます。こうした取り組みは、近年の暑さ対策としても有効です。
さらに、新築や改築を予定している場合には、建物をZEB(ゼロ・エネルギー・ビルディング)にするという選択肢もあります。ZEBとは、省エネや断熱、再生可能エネルギー設備の導入などによって、年間に生み出すエネルギーが消費するエネルギーと同じかこれを上回る建物のことで、光熱費を削減するだけでなく、災害時のエネルギー供給を行うこともできます。
使用する電力をCO2排出量の少ない再エネにする
電力会社から購入する電気にはCO2の排出が伴うことが一般的です。なぜなら、日本で発電される電気のうち、約7割が石炭、石油、天然ガスといった化石燃料による火力発電によるものだからです。
しかし、太陽光発電などの再生可能エネルギー設備を導入したり、電力会社のメニューを切り替えたりすることで、電気の使用に伴うCO2排出量を削減することができます。太陽光発電設備を導入する方法には、自社の屋根や遊休地に設置する方法があります。また、電力会社によっては、CO2排出が伴わないメニューをラインナップしています。他にも、特定の太陽光発電所や風力発電所から電気などを購入する「コーポレートPPA(電力購入契約)」という仕組みも普及しています。
こうしたさまざまな方法を組み合わせて実施することで、電気の使用によるCO2排出量を削減することが可能です。
残ったCO2排出量に対して証書などを活用する
こうした取り組みを行っても、どうしても削減できないCO2排出量に対しては、環境価値を購入することで、実質的にCO2排出量を相殺することができます。例えば、非化石証書は、再生可能エネルギーで発電した電気が持つ“CO2を排出しない”という価値を証書化し、取り引きできるようにしたものです。こうした環境価値だけを取り引きするPPAの仕組みもあり、脱炭素経営を目指す需要家の間で活用されています。
前述した通り、脱炭素に関する企業の自主的な取り組みを後押しする国際イニシアチブがあります。その中から、日本企業が多く参加する主要なものを3つ紹介します。
●SBTSBTは、世界の平均気温の上昇を1.5〜2℃に抑えるというパリ協定の目標達成に向けて、化学的な根拠に基づいたCO2削減目標の設定を支援・認定するものです。SBTでは、毎年2.5%以上のCO2削減を目安として、5〜15年先の目標を設定することが推奨されます。SBTには中小企業版があり、CO2排出量が一定量未満であることや、金融業、石油・ガス業でないこと、親会社が通常のSBTに該当しないことなどの要件を満たす企業が対象となります。
- ●RE100
RE100は、事業を100%再生可能エネルギーの電気で行うことをコミットする国際イニシアチブです。RE100は、年間の消費電力量が100GWh以上(日本企業は50GWh以上)の大企業を対象としています。社会的な影響力が大きい大企業が結集することで、政策立案者に対して脱炭素化を加速させるシグナルを送る狙いがあります。2025年10月現在、94社の日本企業がRE100に参加しています。
- ●TCFD(2023年に解散)
TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)とは、気候変動が企業に与える財務的なリスクや機会について情報開示を求める国際的な枠組みです。金融安定理事会(FSB)が2015年に立ち上げ、2023年に解散しました。2024年からは、IFRS(国際会計基準)が企業の気候関連開示の進捗状況の確認などを引き継いで行っています。IFRSは、気候変動に関する情報開示の基準を統一するためにISSB(国際サステナビリティ審議会)を設置するなど、取り組みを展開しています。
脱炭素経営はあらゆる企業にとって重要な経営課題
大企業だけでなく、中小企業の活動も自然環境の影響を受けています。環境が大きく変化してしまっては、これまで通りの事業活動を続けることは困難になるでしょう。そのため、気候変動対策である脱炭素経営に取り組むことは、あらゆる企業にとって重要だと言えます。脱炭素経営に取り組むことで、企業価値を向上したり、新たな人材との出会いが生まれたりするなど、さまざまなメリットがあります。中長期的な視点で、自社に適した脱炭素経営に取り組み、企業価値の向上と持続可能な成長を目指しましょう。